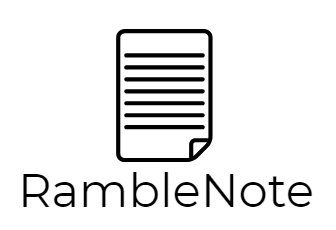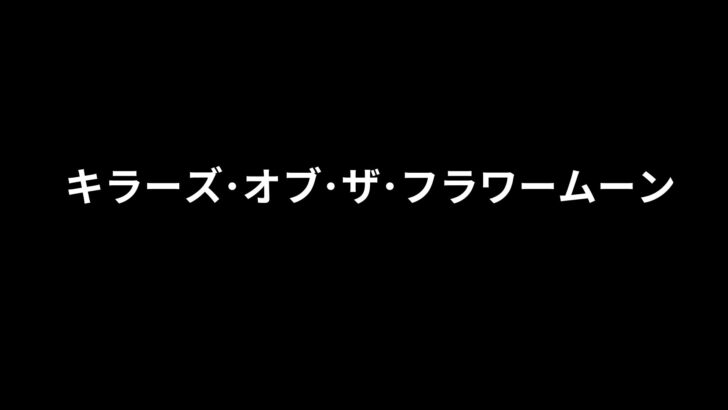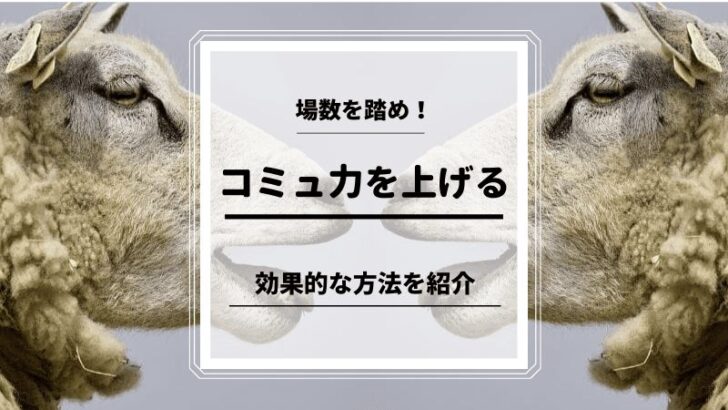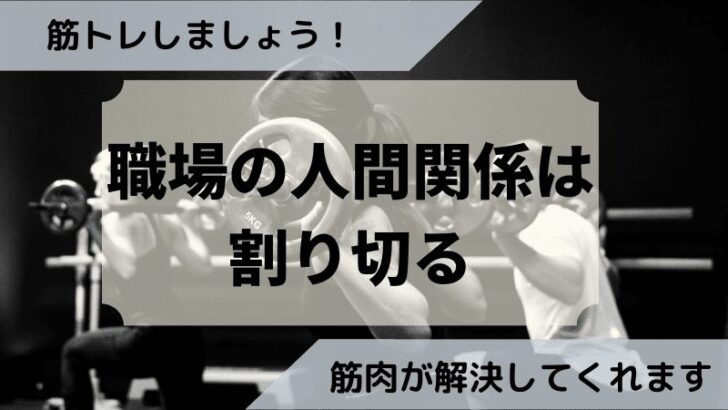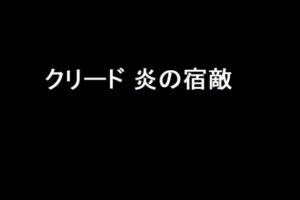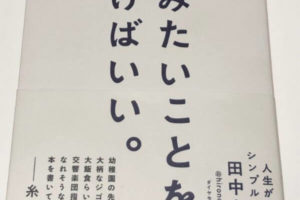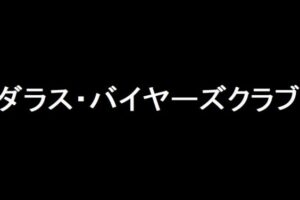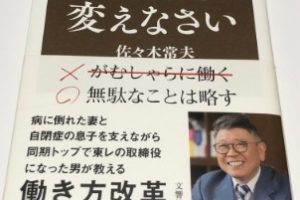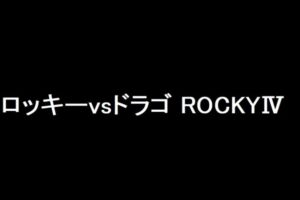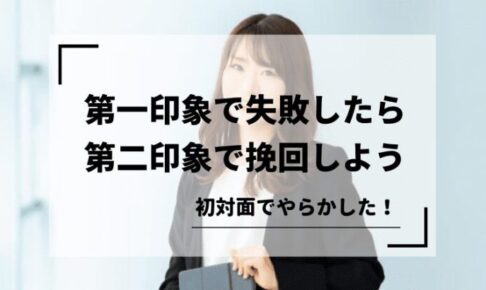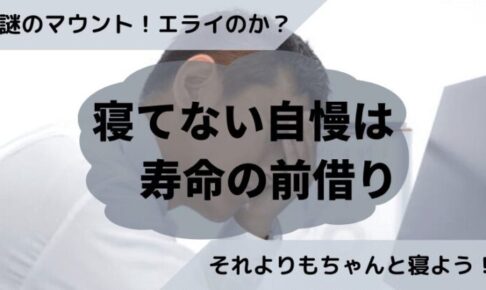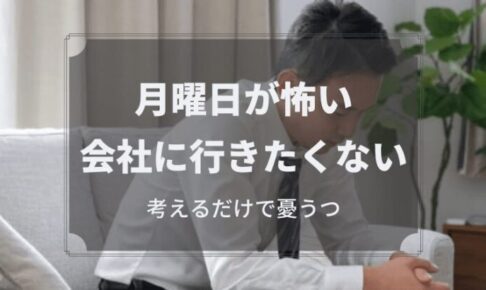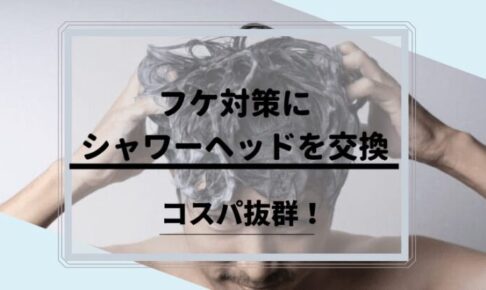近年は『沈黙-サイレンス-』や『アイリッシュマン』など長尺な作品が続いているマーチン・スコセッシ監督による206分のやはり長尺な作品です。
1920年代のアメリカのオクラホマ州オーセージを舞台に、先住民であるオセージ族が次々に謎の死を遂げた怪事件を題材としています。本作の特徴として白人と先住民であるネイティブアメリカンの関係性を従来の白人による救世主の物語にせず、より先住民に寄り添った視点から浮かび上がらせています。

『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』作品情報
【原題】『Killers of the Flower Moon』
【監督】
マーティン・スコセッシ
【出演】
アーネスト・バークハート:レオナルド・ディカプリオ
ウィリアム・”キング”・ヘイル:ロバート・デ・ニーロ
モーリー・バークハート:リリー・グラッドストーン
スコセッシ監督の常連であるデ・ニーロの安定の演技はもちろん、主体性のない凡人役を見事に表現しきったディカプリオの怪演が見ものです。
アメリカ人ジャーナリストのノンフィクション作品『花殺し月の殺人 インディアン連続怪死事件とFBIの誕生』が原作となっています。
『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』ネタバレと感想
20世紀初頭のオクラホマ州。アメリカ政府によってミズーリ州から移住を強いられた先住民であるオセージ族。彼らが所有する土地から石油が産出され莫大な富を得ます。
オイルマネーを得たオセージ族は車を所有し、豪華な衣服を纏い、白人を使用人として雇うなど贅沢な暮らしを享受するが、その富を狙う狡猾な白人が目を光らせている。白人たちは自分たちにとって都合の良い法律を作りオセージ族の財産を管理し、白人の後見人の許可なしではオセージ族の人々は自分たちのお金を自由に使うことができなくなっていました。
戦争から帰ってきたばかりの主人公アーネスト・バークハートは牧場主である叔父のウィリアム・”キング”・ヘイルを頼ってオクラホマの地へ降り立ちました。戦争で腹を負傷し力仕事のできないアーネストは運転手として働くことに。そこで客として出会った先住民の女性であるモーリー・カイルと恋に落ち、やがで結婚し二人の間には子どももできました。

画像提供Apple
ヘイルはオセージ族からも絶大な信頼を得ていましたが、その実狙いは彼らの莫大な財産でした。オセージ族と結婚すれば受益権が発生しやがて財産が転がり込んできます。
ヘイルの企みによりやがてモリーの家族も含め次々とオセージ族の人間が不可解な死を遂げてゆきました。アーネストもヘイルの指示で事件に関わるようになります。事件が起きてもロクに捜査もされないことに不信感を持ったオセージ族は探偵を雇いましたが無駄に終わるのでした。
モリーは糖尿病が悪化するがインスリンの注射を医師ではなくアーネストに任せます。やがてヘイルからインスリンに謎の薬を混ぜて注射するよう言われましたが、それによりモリーの体調は悪化していくのでした。
ある日モリーの妹とその夫の家が爆破されます。オセージ族はワシントンへ赴き大統領に事件の捜査を嘆願し連邦捜査官がオセージへ派遣されてきます。

画像提供Apple
アーネストはモリーを愛しつつもヘイルには逆らえず彼の企みに巻き込まれていき、ついにヘイルとともに逮捕されてしまいます。初めはヘイルに従っていたアーネストだが獄中で彼の子どもが亡くなったことが伝えられると、ついに裁判での証言を承諾するのでした。
アーネストはモリーから注射の中身を問われるがインスリンだと答えました。その言葉を聞いたモリーは無言でアーネストのもとから立ち去ってしまいます。
一転ラジオドラマの舞台にシーンが移り事件の顛末とヘイル、アーネスト、モリーのその後が語られました。
序盤での提示
序盤でふたつのポイントが観客に提示されています。通常の映画作品とは違う主人公の人物像と一般には知られていない意外な歴史的事実です。
- アーネストの主体性の無さ
- 裕福なネイティブアメリカンの存在
アーネストが群衆の中を歩いているシーンでは自らの意思というよりは周りに流されているようにも見え、更には自分とは関係ないケンカに理由もなく飛び込もうとしています。話し方ひとつ取っても、とてもではないですが知的には見えません。本作の主人公が決してスーパーマンやヒーロー的な人物ではないことがわかります。
意外な事実として観客に提示されているのは虐げられているはずの先住民が白人よりも裕福な暮らしをしているシーンです。一般的に思われている貧しい先住民というイメージを覆すこの社会的な構図が本作での事件のモチーフとなっています。

画像提供Apple
レオナルド・ディカプリオの怪演
美少年から出発し若い頃は二枚目役を演じてきたレオ様ですが、近年は落ち目の役者や悪徳農園主など見た目のカッコよさとは無縁の役柄を好んでいるようで、本作のアーネストも愚かで主体性がなく薄っぺらい人物像を見事に演じ切っています。
叔父のヘイルには逆らえずヘマを犯した際には折檻までされる始末。金と女が好きで強盗や殺人依頼もやるようなモラルの無さと同時に、先住民に対する偏見を持たず妻のモリーや子どもたちを心から愛しているように善と悪を併せ持つような人間臭さを持っています。どう見ても思慮が浅い人物ではあるのですが、彼は彼なりに葛藤と戦ってもいます。
ディカプリオの演技力は冴えわたっており、とことん凡庸だが内に秘めた複雑さも滲ませるといった難度の高い演技をやってのけました。主役とはいえ力量のない役者だと映画の中に埋もれてしまうであろう役柄をこれだけ表現できるのは非凡な才能のなせる技です。
ネイティブアメリカンへのリスペクトとただの悪
本作ではネイティブアメリカンへの丁寧な描写が散見されます。超自然的な儀式を美しい映像で映し出し、話し合いやあくまでも法に則った抗議を行うなど文明人としての思慮深い行動が取られていました。
白人文化に浸食されつつも、伝わり継がれてきた自分たちのアイデンティティを失うまいとする姿は美しくもあります。一方で富を享受したが故のアルコールやうつ病、糖尿病といった問題が先住民を蝕んでいく様子も描写されていました。
序盤では先住民の女性たちが白人男性を品定めをしているシーンもあり、一方的に搾取されるだけの存在として描いているわけではありません。

画像提供Apple
一方で白人側は選民意識と富に対する嫉妬が結びつき短慮な行動をおこし、ネイティブアメリカンの人命をいとも簡単に奪っていく。そこに見られるのはスコセッシ監督がこれまで描いてきた人々を魅了する華のある悪とは全く異質の救いようもないだたの悪であり観客の共感を寄せ付けないものです。
法律もネイティブアメリカンにとっては平等とは言えず白人たちにとって都合の良い社会システムでしかありませんでした。
財産は持っているのに先住民は無能力者とされ、お金を引き出す際には白人の後見人の許可が必要です。無能力者とされているモリーは登場人物の中では最も落ち着いて知的な雰囲気を纏った人物に描かれています。アーネストとどちらが無能力者かは一目瞭然です。
更には殺人がおきても被害者が先住民だと捜査は行われません。ワシントンに直談判に行ってやっとまともな捜査が行われるといったあんばいです。
一見ネイティブアメリカンと白人が共存しているように見えても、実際には社会そのものが白人の都合よく組み立てられており、ネイティブアメリカンは搾取の対象でしかありませんでした。
そして彼らの悲劇は娯楽の対象とすらなり得ます。ラストでのラジオショーがそのことを暗示しているようです。
主人公の設定による黒歴史の浮かび上がらせ方
様々なところで語られていますが、当初主人公は捜査官のトム・ホワイトでディカプリオが演じる予定でした。ですがこの作品の焦点はどこにあるのか、どう焦点を当てるべきかを考えた結果ディカプリオ本人がアーネスト役を希望したとのことです。
それにより脚本は大幅に書き換えられ、ありきたりな白人による事件解決の物語にするのではなくよりオセージ族に寄り添った視点になりました。もっとも本当にオセージ族の立場に近づくならモリーを主人公にするべきだったという意見もありますが、そうなると被害者側からの単純な描写になってしまった可能性もあります。

画像提供Apple
アーネストがヘイルの指示で毒物とうっすらわかっていながらモリーの注射に混入するシーンについては心理描写が省かれていました。その姿には自らの意思で判断することなく悪に身を任せていく人間の弱さが表れており、自分自身への責任感と誠実さは感じられません。
白人の救世主を主人公にしてしまうと作品の主張にどうしても反省と贖罪が含まれてしまいますが、愚鈍な人物を主人公に置き換えたことで、事件が起こった事実を余計なニュアンスを最小限に抑えて俎上に乗せる効果がありました。
白人による自己満足的作品に陥るのではなく、この陰惨な事件を先住民に近い視点で衆目に晒すことでアメリカの黒歴史への解答を見出そうという姿勢が伺えます。
ハエとショミカシ
アメリカ社会に根深く食い込んだ差別意識はハエのように払っても払っても纏わりついてきます。アーネストが振り払おうとしたハエは先住民にたかる白人のように思えます。
モリーがアーネストに呼びかけたショミカシはオセージ族の言葉でコヨーテを意味します。オセージの人々にとっては白人はずる賢いコヨーテのような存在です。オセージ族の人々にとっては白人はまさにコヨーテのような存在であり、モリーはそのことを見抜いていたゆえの言葉でした。
まとめ
アメリカに限らず歴史上に起こった惨劇にどのようにスポットを当てていくかを考えさせられる作品です。
デ・ニーロの安定の演技はいつもながらさすがですが、やはりディカプリオの表現力には目を瞠るものがります。モリー役のリリー・グラッドストーンの気品のある素晴らしい演技にも注目です。